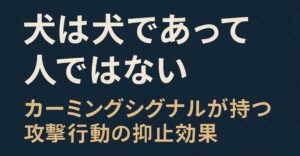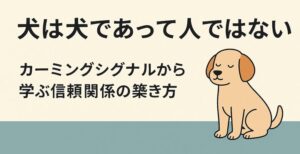ドイツは「犬に優しい国」として世界的に知られています。街中のカフェやレストラン、緑豊かな公園、そして人々が行き交う駅や広場まで、犬が人間社会に自然に溶け込んでいる光景を目にすることができます。
しかし、この「犬に優しい社会」は、単なる文化や人々の気質だけで成立しているわけではありません。犬と人が共に暮らすために必要な制度が整備され、その中で犬が社会的に認められてきました。その代表的なものが犬税(Hundesteuer)です。
日本には犬税が存在しないため、多くの方にとっては耳慣れない制度かもしれません。しかし、犬税はドイツにおいて200年以上存続し、犬と人の共生を支える文化的・社会的な基盤として機能してきました。
本記事では、Hundesteuerの仕組みや歴史、社会的意義、そして一般財源であることの二面性について詳しく解説し、最後に筆者自身の考察も交えて「犬税が持つ意味」を考えてみたいと思います。
Hundesteuer(犬税)の基本的な仕組み

犬にだけ課される特別な税
Hundesteuerは、犬を飼っている飼い主に課される地方税です。猫やウサギ、小鳥など他のペットには課されません。これは、犬が散歩や外出を通じて日常的に公共空間を利用し、社会に与える影響が他のペットよりも大きいと考えられているためです。
税額の目安
税額は全国一律ではなく、市町村ごとに異なります。相場は以下の通りです。
- 1頭目:年間100〜150ユーロ(約16,000〜24,000円)
- 2頭目以降:割増(例:180ユーロ以上)
- 闘犬指定犬種:600〜1000ユーロを超える場合もある
犬の頭数が増えるほど税額が上がる仕組みになっており、無責任な多頭飼育を抑制する効果があります。
Hundemarke(犬税メダル)
犬税を納めると自治体から「Hundemarke」と呼ばれる金属製のメダルが交付されます。犬の首輪に装着することが義務付けられており、納税済みであることを示す証明書の役割を果たします。警察や職員から提示を求められることもあり、日本の「狂犬病予防注射済票」に似ていますが、税金の支払い証としての性格が強いのが特徴です。
犬税メダルではありませんが、万一のときのための迷子札。必須アイテムです。
免税・減税のケース
一律に課税されるわけではなく、社会的に意義のある役割を果たす犬や保護犬には優遇措置があります。
- 盲導犬・介助犬・聴導犬 → 非課税
- 警察犬・救助犬 → 非課税
- 動物保護施設から譲渡された犬 → 一定期間減税
このように、Hundesteuerは「犬を飼うことは責任を伴う」という意識づけであると同時に、社会的に価値ある活動を支援する仕組みでもあります。
Hundesteuerの歴史
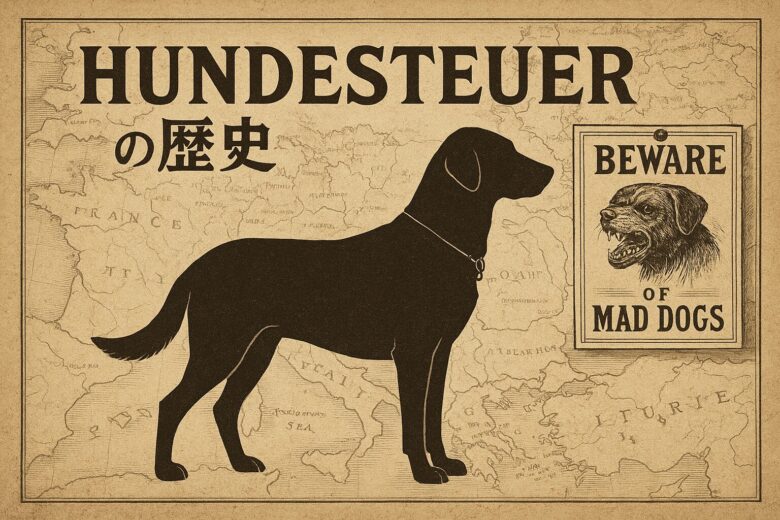
Hundesteuerの導入は19世紀初頭にまでさかのぼります。当時ヨーロッパでは狂犬病が深刻な問題であり、犬の数を制限し、管理する必要がありました。
犬税導入の目的は以下の通りでした。
- 狂犬病の感染拡大防止
- 放し飼いによる咬傷被害の抑止
- 自治体の財源確保
狂犬病の脅威が薄れた後も犬税は廃止されることなく、制度として残りました。現在では「犬を飼うことは社会的責任を負うこと」という意識を社会全体で共有するための象徴的な制度となっています。
Hundesteuerの運用と地域差

自治体ごとの税額の違い
ドイツは連邦制国家であるため、税額は州や市町村ごとに異なります。
- ベルリン:1頭目120ユーロ、2頭目以降180ユーロ
- ミュンヘン:1頭目100ユーロ前後だが、複数飼育の割増率が高い
闘犬種への高額課税
一部の犬種、いわゆる「危険犬種(Kampfhunde)」については、一般犬の数倍にあたる高額な税率が設定される場合があります。これは飼育を経済的に抑制する狙いがありますが、「犬種差別ではないか」という批判もあります。
Hundemarkeによる管理
犬税を払うと交付されるHundemarkeは、飼い主の特定を容易にする役割も持っています。迷子犬やトラブル時に「誰の犬か」をすぐに確認できるのは、行政にとっても大きな利点です。
Hundesteuerをめぐる議論

賛成派の主張
- 公共サービスの費用を犬飼育者が公平に負担できる
- 無責任な飼育や放棄を抑止できる
- 飼い主の責任意識を高め、社会全体のマナーを向上させる
反対派の主張
- 猫や他のペットに課税されないのは不公平
- 税収規模は小さく、自治体財政に大きな効果はない
- 行政コストに対して効果が薄い
特に「犬だけに課税するのは不公平ではないか」という議論は根強いですが、犬が公共空間を日常的に利用するという特性を考えれば、合理的だと考える人も多いのです。
Hundesteuerがもたらす社会的意義
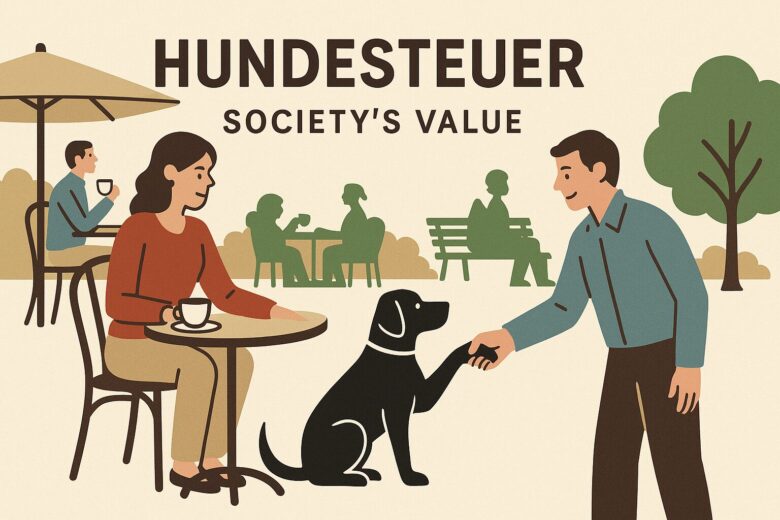
Hundesteuerは財源確保の手段であると同時に、社会に以下のような影響を与えています。
- 飼い主の責任意識向上
犬を飼うことには税の支払いが伴うという認識が、安易な飼育や放棄を減らします。 - 公共空間での安心感
登録と課税によって「犬は管理されている」という社会的信頼が醸成され、犬が公共空間に受け入れられる基盤になります。 - 犬関連インフラ整備の財源
一般財源ではありますが、公園清掃やドッグラン整備に充てられる場合もあります。 - 社会的象徴性
犬を「家庭内の存在」から「社会全体を支える存在」へと位置づける象徴的な制度として機能しています。
犬税が「一般財源」であることの二面性

Hundesteuerは目的税ではなく一般財源です。そのため、犬税の収入は必ずしも犬関連施設に充てられるわけではなく、道路、学校、文化施設など社会全体のために使われます。
批判的な見方
- 犬税なのに犬関連に使われていないのは不透明
- 実態としては「財源確保のための名目」にすぎないのではないか
肯定的な見方
- 犬専用の費用に限定されないからこそ、犬と飼い主が社会全体を支える存在となる
- 税を払うことで、犬飼育者が社会の一員として正当性を持つ
つまり、犬税は財政効果以上に、「犬は社会全体の一部である」という象徴性を帯びているのです。
筆者の考察(私見)
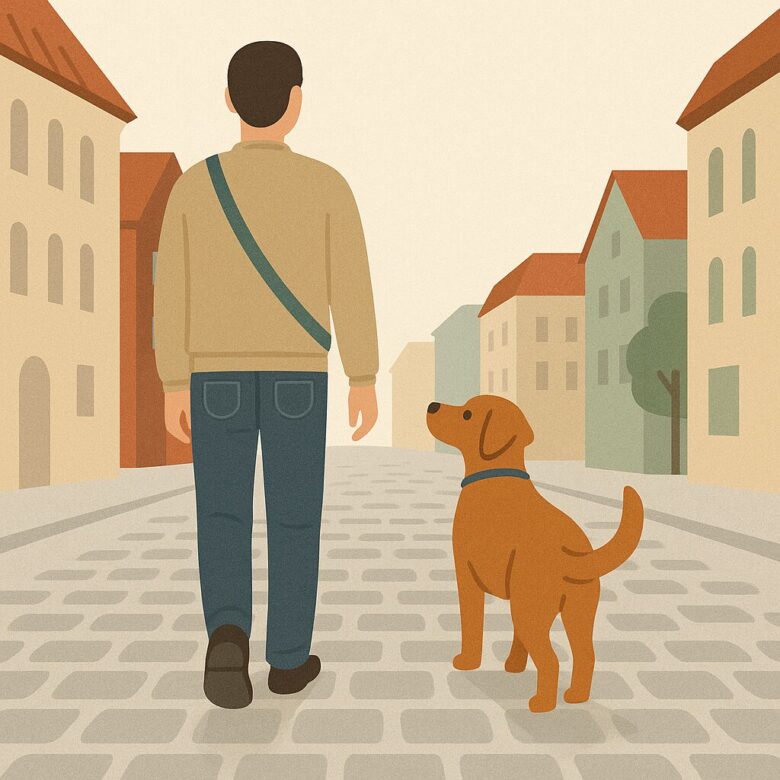
筆者は、犬税には課題があるものの、犬を飼う人々にとって有益な側面があると考えます。
近年、公園や公共施設で「犬不可」とされる場所が増えています。これは犬を飼わない人々が「自分たちの税金で犬関連の費用を負担している」と感じることが一因かもしれません。犬税を導入し、その収入を社会全体に還元すれば、不公平感は薄れやすいでしょう。
また、犬税を払うことで飼い主は発言権を得ます。「犬も利用できる公園を増やしてほしい」「ドッグランを整備してほしい」といった要望を正当に主張できるようになるのです。
一方で、重要な懸念点もあります。徴収や管理のコストが税収を上回る可能性です。日本の犬飼育頭数や自治体の規模を考えると、徴税のための事務コストやシステム整備、人件費が膨らみ、「思ったほどの財政効果が得られない」リスクがあります。これはすでに反対派が指摘している論点でもあり、もし導入するなら効率的な徴収体制を整えることが前提になるでしょう。
さらに、税を払っているからといって「好きにしていい」という誤解が広まる恐れもあります。飼い主のマナーと責任意識の徹底がなければ、犬税が逆効果になることさえ考えられます。
犬税は、犬を単なる家庭内の存在から「社会を支える一員」へと位置づける制度です。その意義を理解することは、犬と人がより良い関係を築くための大きなヒントになるのではないでしょうか。
まとめ
犬は単なる家庭のペットではなく、社会全体を支える一員になり得る存在です。犬税(Hundesteuer)の仕組みは、そんな犬と人との関係を制度として示してくれています。
我が家の犬を“ペットから社会全体を支える一員に
その意識を持つことこそ、犬と人が共により良い社会を築く第一歩なのかもしれません。」






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000871&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0103081599.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000909&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104307039.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000905&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104052204.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000816&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102355854.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099671821.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101358042.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000882&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0103358337.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)