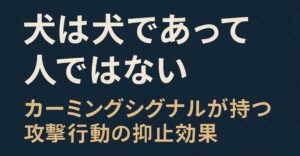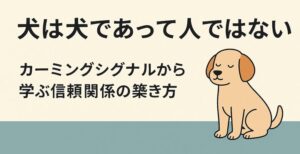現代の犬のしつけにおいて、おやつ(フード)を使った報酬トレーニングは広く普及しています。もちろん、それ自体有効な場合もあります。しかし、おやつに頼るあまり、「飼い主自身の存在や感情表現」がご褒美としての価値を見失われがちです。実は、心理学・行動学・脳神経科学の研究が次々に明らかにしているのは、飼い主の豊かな感情表現こそが、犬にとってもっとも深く、持続的な“ご褒美”になるという事実です。
本記事では、3つの科学的視点からこのテーマを掘り下げます。
心理学的視点──信頼と絆が行動を変える

● ソーシャルリファレンシング:飼い主の感情が“行動の手がかり”に
犬は、不安や迷いを感じたとき、自分の行動をどうするかを「他者の感情を手がかりに」決めることがあります。これを「ソーシャルリファレンシング(社会的参照)」と呼びます。
心理学者Merolaら(2012)の研究によれば、見慣れない物体を前にした犬は、飼い主が笑顔でポジティブな声をかけた場合、恐怖心なく近づき、物体と接する時間も長くなったそうです。逆に飼い主が困惑した表情で不安げな声を発した場合、犬は近づこうとせず、物体との関わりも控えめになりました。
このように、飼い主の喜怒哀楽は犬にとって「安心か・危険か」の重要なシグナルになっており、感情表現そのものが犬の行動を導く“報酬”になっているのです。
欧米人は感情表現が豊かな方が多いので、犬のコントロールがしっかりできていたりします。一方、日本人は無表情に近い方が多いので、犬も感情が読み切れず、困惑していることが多いです。
● 感情が学習効果に与える影響
2024年、Bräuerらは実験で、映画を見て感情状態を操作された飼い主が犬に指示を出した場合の犬の行動を調査しました。結果、飼い主が幸福な状態の時には犬の学習意欲が高まり、命令への反応も良好だった一方、飼い主が悲しみに沈んでいると、犬の協力度が下がったのです。
つまり、飼い主が前向きな感情を表現することで、犬の学習意欲や信頼関係が強化されることがわかります。
行動学的視点──「優しい声」「笑顔」「アイコンタクト」が生むしつけ効果
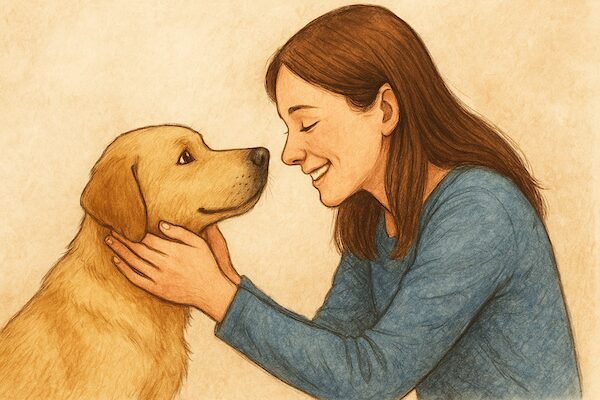
● 声のトーンが犬のパフォーマンスを左右する
2023年、ブラボ・フォンセカらは、異なる声色で指示を出す訓練セッションを行い、「優しい声(高くて抑揚のある話し方)」が犬の反応にどのような影響を与えるかを検証しました。
結果は明らかで、優しい声の時間が長いセッションでは、犬の尻尾振り、トレーナーへの接近行動、指示の正答率が上昇。一方、怒鳴るような口調では反応が悪化しました。
これは「感情豊かな声」が犬の気持ちを前向きにさせ、しつけの成功率を高めることを示しています。
女性が愛犬を叱るときはできる限り低いトーンで、男性が愛犬を褒めるときは、できる限り高いトーンで発することが重要です。

● アイコンタクトがオキシトシンを増やす
永澤 美保(2015)らの研究では、飼い主と犬が見つめ合うことで、オキシトシン(愛着ホルモン)が飼い主・犬の双方で上昇することが明らかになっています。
このホルモンは「安心」「信頼」「親密感」に関連しており、アイコンタクトという“感情的な交流”が犬にとって強力な報酬となることを示しています。
第3章:脳神経科学的視点──感情表現が犬の脳をどう変えるか

● 声の内容とトーンの“両方”を犬は処理している
2016年、AndicsらのfMRI研究は、犬の脳が「褒め言葉」と「声の調子」を別々の領域で処理し、両方がポジティブなときにだけ報酬系(腹側線条体)が強く反応することを明らかにしました。
これは、単に「褒めてる言葉」だけでなく、“嬉しそうな声色”であることがセットで初めて犬の脳が“ご褒美だ”と認識することを意味しています。
● おやつと同等かそれ以上の価値がある「褒め」
Cookら(2016)の実験では、犬が「餌のある道」と「飼い主が褒めてくれる道」のどちらに向かうかを比較したところ、多くの犬が餌よりも飼い主の称賛を選んだという結果が得られました。
実験では、fMRI装置で脳活動を計測しながら、犬に「餌報酬」と「飼い主の褒め」を予告する合図(中立的なオブジェクト)を提示。その後、実際に迷路装置を使い、餌と飼い主のどちらの方向に向かうかを測定しました。その結果、犬の尾状核(報酬系)は両方の報酬に反応しましたが、飼い主の褒めを示す合図に強く反応した犬ほど、実際の選択でも飼い主を優先する傾向が顕著でした。
特に印象的なのは、最も「褒め」に反応した犬では、80〜90%の確率で飼い主の称賛を選択したこと。これは単に訓練の成果ではなく、犬が「飼い主の感情的なフィードバック」を本質的な報酬として受け取っている証拠とされています。
著者らはこの結果について、「犬にとって社会的報酬は非常に価値が高く、人間が褒められて嬉しいと感じるのと近い情動的プロセスが働いている可能性がある」と述べており、犬の脳が“愛情や称賛”を食べ物と同等、もしくはそれ以上のものとして評価することがわかります。
この研究は、おやつに頼らないしつけの実践において極めて重要な示唆を与えており、飼い主の感情そのものが「学習を強化する報酬」として生理的にも行動的にも機能していることを裏付けています。
そもそも、犬育てのプロである母犬はおやつを使って教育をしません。
第4章:なぜ「感情」が持続可能なご褒美になるのか

- おやつ:即効性はあるが、一貫性・長期的な絆は生みにくい。
おやつは飽きがきます。
- 感情表現:犬にとって個体識別的なご褒美であり、飽きが来ない。
- スキンシップ・アイコンタクト・声・表情の複合刺激が脳内報酬系・オキシトシン系を刺激。
- 信頼感が高まることで、新たな指示への受容性が増す(=しつけが容易に)。
つまり、感情表現は「心の栄養」として犬に刻まれ、しつけ効果の持続に寄与します。
第5章:おやつ“だけ”に頼らないしつけのすすめ

現代は“おやつでなんとかなる”という考えが主流になりがちですが、それは本来の人と犬の関係性を浅くしてしまうこともあります。重要なのは、「おやつ+感情表現」あるいは「感情表現を中心に据え、おやつは補助」という視点です。
愛犬は飼い主の笑顔・優しい声・一貫したリアクションに強く反応し、そこから「安心」「信頼」「意欲」を学びます。
おやつに依存すると、それがないと飼い主の言うことを聞かない犬もいます。まさに「おやつの切れ目が縁の切れ目」です。おやつに頼らないといけない関係って家族といえますか?
第6章:犬種・年齢による反応の違い
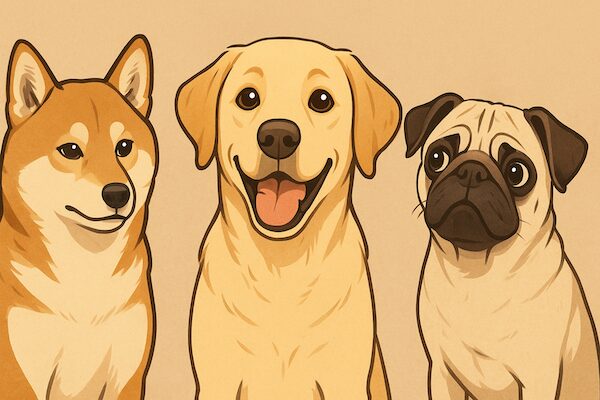
● 犬種による感情表現への感受性
作業犬種(ボーダー・コリー、ラブラドール・レトリバーなど)
- 高い社会的認知能力を持ち、人間の感情・表情・指示に敏感。
- 飼い主の感情表現を「手がかり」として積極的に利用しやすい(Miklósi et al., 2003)。
柴犬・秋田犬などの日本犬
- 自立心が強く、感情表現に対する反応に個体差が大きい。
- 表情よりも一貫性のある行動や声かけに対して安定して反応。
呼び戻しに苦戦している飼い主が多いと、私も経験上感じています。
パグ・フレンチブルドッグなどの短頭種
- 顔の表情認識は不得意でも、声の抑揚やボディランゲージに敏感。
- 感情伝達には音声トーンの変化が効果的。
● 年齢別の傾向としつけ感受性
子犬(〜6ヶ月)
- 社会化期にあるため、オキシトシン感受性が高い。
- 飼い主の感情を学習に紐づけやすく、ポジティブな感情表現が強力な報酬となる(Topál et al., 2005)。
早期の社会化教育は非常に重要です。

青年期(6ヶ月〜2歳)
- 自我の芽生えや反抗期的な行動が見られやすい。
- 気分のムラがあるため、感情表現の安定性がカギ。
- おやつと感情表現の併用が効果的。
成犬(2〜6歳)
- 行動が安定し、飼い主との信頼関係が成熟。
- 感情表現の質や一貫性が、学習の強化や維持に効果的。
高齢犬(7歳〜)
- 認知機能の衰えが始まるが、感情的な交流には深い安心感を示す。
- 表情よりも声やスキンシップが重要な刺激となる。
おやつに依存した関係性作りしかしてこなかった場合、食が細くなった高齢犬とのコミュニケーションが取りづらくなります。また、アレルギーを持った犬などは、そもそもおやつを与えてのトレーンングに不向きです。
おわりに──愛情は脳に届く、最高の“ご褒美”
感情豊かな飼い主は、犬にとって“最強のご褒美装置”です。しつけに悩むときほど、「自分はどんな顔で、どんな声で、どんな気持ちで接しているか」を見直すことで、犬との関係性は大きく変わってきます。
おやつも道具も使い方次第。けれど、それを使う「あなたの感情」こそが、本当のご褒美であることを、科学が証明しつつあるのです。
私は喜怒哀楽を最大限表現して、褒める、遊ぶ、叱るをバランスよく、それぞれ必要な場面で使い分けることがとても重要だと考えています。
しつけは愛犬の命を守るために行うことだと私は考えます。

参考文献
- Merola, I., Prato-Previde, E., & Marshall-Pescini, S. (2012). Dogs’ Social Referencing towards Owners and Strangers. PLOS ONE, 7(10), e47653. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047653
- Bräuer, J. et al. (2024). Dogs distinguish authentic human emotions without being empathic. Animal Cognition.
- Bravo Fonseca, R. et al. (2023). The Power of Discourse: The Effects of Training Voice Tone on Dogs’ Behavior. Animals, 13(2), 259.
- Nagasawa, M. et al. (2015). Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds. Science, 348(6232), 333–336. https://doi.org/10.1126/science.1261022
- Andics, A. et al. (2016). Neural mechanisms for lexical processing in dogs. Science, 353(6303), 1030–1032. https://doi.org/10.1126/science.aaf3777
- Cook, P. F. et al. (2016). Awake canine fMRI predicts dogs’ preference for praise versus food. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(12), 1853–1862. https://doi.org/10.1093/scan/nsw102
飼い主の魅力で愛犬の命を守るためのトレーニング方法をお教えします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000576&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099377248.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000906&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104061573.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000905&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104052204.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000837&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102937302.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102947074.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099671821.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000909&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F12168550%2Fimgrc0104307039.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)