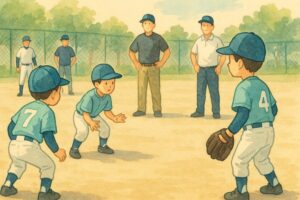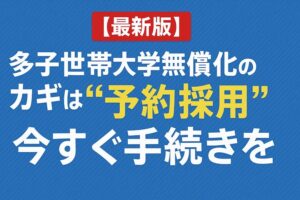兄弟が多くても家は回る? わが家では“家事=報酬”の制度で子どもたちが自ら動き、責任感と自律を育んでいます。報告制・報酬単価制・チェック制度で、ただの手伝いを“家庭の戦力”に。子どもの性格まで見えてくる、実践的な仕組みをご紹介します。
はじめに:「兄弟が多い」と家事も想像以上

5人兄弟、犬2頭、カメ1匹、文鳥1羽、メダカ多数——。
そんなわが家では、正直、親だけで家事を回すのはもう無理です。洗濯・トイレ掃除・ゴミ出し・犬のトイレ処理・食器洗い…、どれも毎日発生し、誰かがやらなければ生活がまわりません。
そこで導入したのが「家庭内お手伝い=報酬制(単価制)」という仕組みです。
お金をもらうためのバイトのようでありながら、家庭の運営を支える責任ある役割でもあります。
現在、上は大学生1年生。下は小学校6年生ですが、6年ぐらい前からこの制度は運用開始しています。末っ子が低学年のときはできる限りシンプル且つ単発作業を割り振っていました。
制度のルール①|お手伝い=義務だけど報酬ももらえる

わが家の基本方針はこうです:
家の手伝いは “家族の一員としての義務”なので必ずやらなければいけない。
でも、 “報酬”として正当に評価。
たとえば、
- 食器洗い
- 洗濯
- トイレ掃除
- 風呂掃除
- リビング掃除
- 階段・廊下掃除
- ゴミ出し
- 玄関掃除
- 犬のトイレ処理
- 亀の飼育ケース掃除
- 洗車 など。
仕事ごとに報酬額(数十円から数百円)を明確に設定しています。
我が家にお小遣い制度はありません。ですから、働かないと祖父母などからいただくお年玉などで1年間やりくりしなければなりません。
制度のルール②|報酬は「報告」してはじめて発生する

とても重要なのがこのルール:
✅ 「報告して確認されてはじめて報酬が発生する」
LINEなどで「○○掃除終わりました」と申告。親が内容を確認します。報告がなければ無効。中途半端なら「やり直し」。
つまり、仕事をやり切る → 報告する → チェックされる → 報酬を得る
このプロセスを通して、責任と信頼の意味を体験してもらいます。
やってもないのに報告してくる子もいれば、やったのに報告をしない子もいます。笑
制度のルール③|実績がすべて

- 「前借りで○○円ちょうだい」は、実績がない子は却下、ある子は渡します。
- 確実、丁寧にする子には優先的に希望の仕事を割り振り、報酬アップを行っています。
なお、子どもが交渉をしてくるのは自由です。私や妻につき返されることも多いですが、それも含めて学びだと思っています。
制度の工夫|ムラのある子、コツコツ派、前借り交渉タイプも見えてきた

この制度を回すなかで、子どもの性格がよく見えるようになります。
- 行動派タイプ:「1円でも多く稼ぎたい」と高単価を狙ってどんどん動く
- 淡々派タイプ:「必要な分だけやれば十分」とルーティン化して安定
- ムラタイプ:1週間がんばったら、次週はゼロ(声かけで立て直し)
- 交渉タイプ:「来週まとめてやるから前借りして」
- 忘れやすいタイプ:「言われないとやらない」「申告しない」など
こうした性格傾向を知ることで、親の対応や声かけの工夫も自然に変わっていきます。
自律の芽|“言われなくても動く子”を育てるために

この制度の運用で重視しているのは、「親が“○○した?”と聞かなくても、子どもが自分から動くこと」。
報酬が明確で、仕事が“早い者勝ち”で、“見える化”されているから、
子どもたちはだんだんと「言われる前にやる」のが当たり前になってきました。
ただし、やっていなければ指摘するのも重要です。
放置すると「やらなくてもいい」と誤解されてしまうため、「これはあなたの担当だよね?」と冷静に、でも確実に伝える姿勢も忘れません。
まだまだ、自分から動くことができない子もいますが根気よくです。
気づいたら、子どもたちは“家の戦力”に

習慣化されるまで言い続けるのは大変でしたが、今では家の中の基盤です。
- 犬の排泄処理を忘れると、室内が臭う
- トイレ掃除を誰もやらないと不衛生
- ゴミ出しが遅れれば家族が困る
つまり、子どもたちはただの「お手伝い要員」ではなく、
「家庭を支える実働部隊」になっています。
まとめ|家庭運営も人生の基礎づくりも、この制度で学んでいる

- 「お金は働いて得るもの」
- 「仕事にはていねいさが必要」
- 「報告・責任・確認が信頼につながる」
- 「家族の中でも“役割”があること」
この制度は、家を回す手段であると同時に、
結果として、子どもたちにとっての“人生の縮図”を体験する場であって欲しいとも願っています。
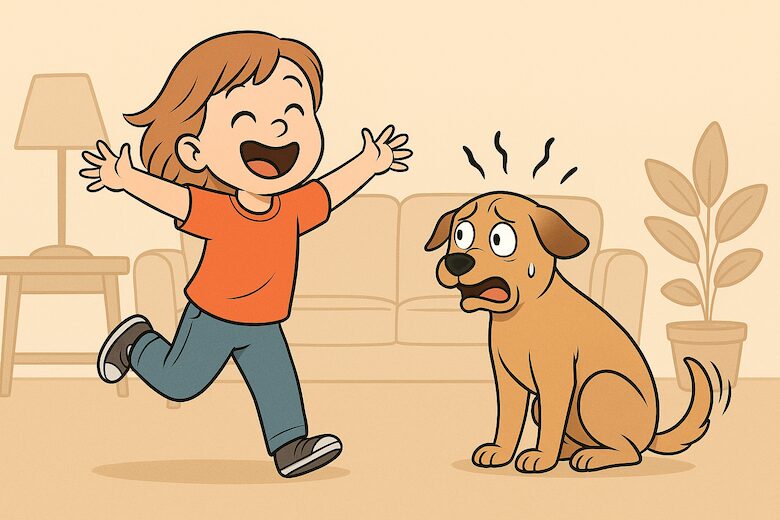


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000604&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11432963%2Fimgrc0099685034.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000772&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101349510.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000867&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0103020825.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000845&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102947074.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000799&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11844432%2Fimgrc0101709613.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000820&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102725512.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e1b60c2.82214fdc.4e1b60c3.3afd90ba/?me_id=1426672&item_id=10000826&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenjoylife-sun%2Fcabinet%2F11958081%2Fimgrc0102760522.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)